塩が野菜をどのように変える?効果と使い方に関するトリセツ

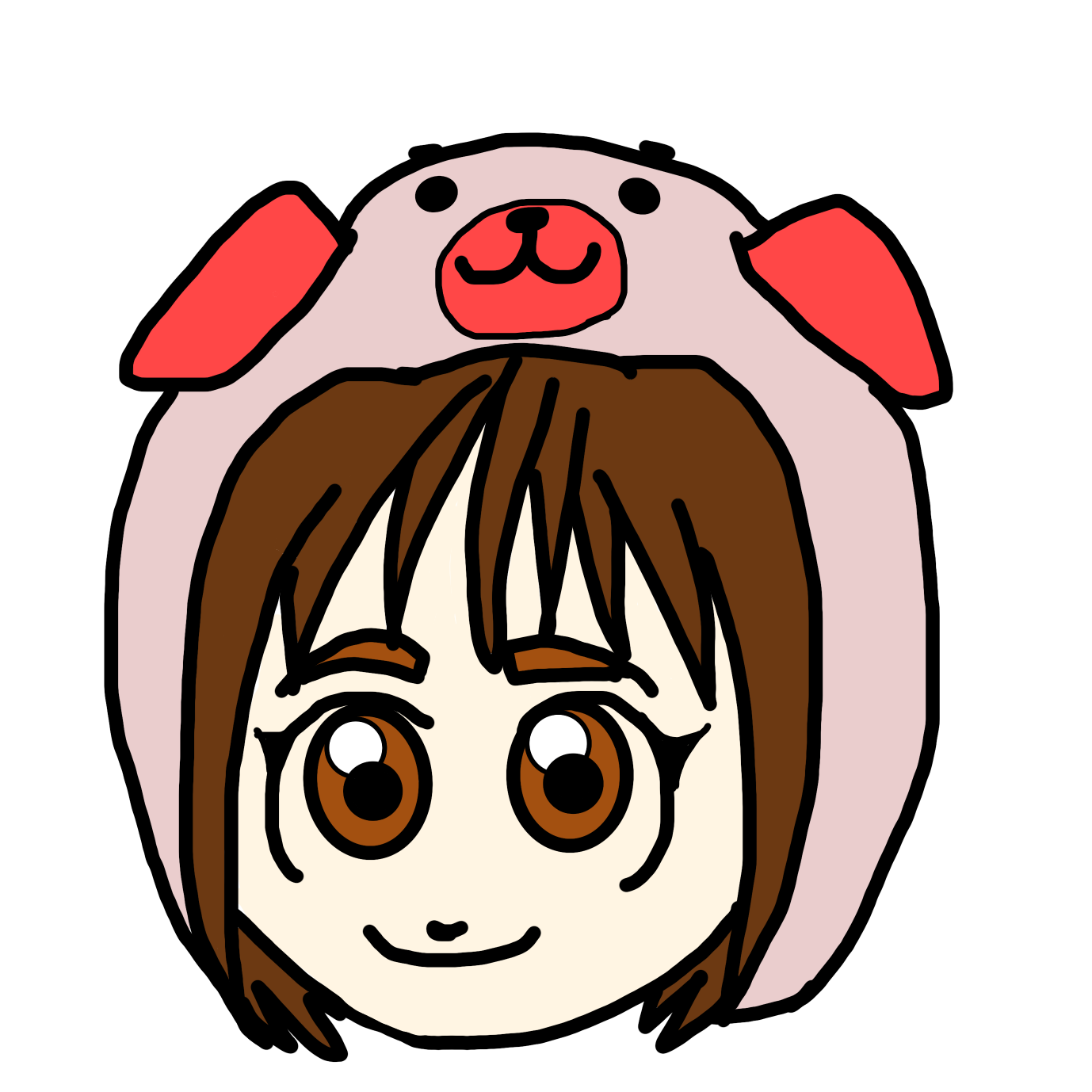
なんで野菜を茹でる時に塩を入れたり、サラダの時に塩もみをしたりしなかったりするの?

緑色の茹でる時に塩をいれるときれいに茹でれるよ。
サラダの時は、しんなりさせたいなら塩もみして、シャキシャキさせたいなら塩もみしないといいよ。
塩は調味料として以外にも様々な使い方があります。
今回は、その中の一つとして野菜に使った時の良い効果を紹介します。
野菜に塩もみをすると浸透圧の影響で脱水作用が働いたり、クロロフィルという成分に良い影響を与えたりするので覚えておくと1ランク上の料理を作ることができるでしょう。
代表的なものを紹介します。
ほうれん草をゆでるときは塩で変色を防ぐ

野菜の緑色は、クロロフィル(葉緑素)という色素によるものです。
このクロロフィルという成分は、熱に弱いという特徴があるため、長時間過熱を続けると分子内のマグネシウムがはずれて色あせてしまい、褐色のフェオフィチンというものになります。この変化は、生野菜に含まれる酸化酵素(オキシダーゼ)によって促進されます。
青野菜を茹でるときは、あらかじめ沸騰した湯の中に入れ、少しでも加熱時間を短くしましょう。
ほうれん草などの青野菜を水から茹でると、温度が高まっていく間に酸化酵素が働いて褐色がすすんでしまいます。しかし、熱湯の中に入れることで高温のために酸化酵素の作用が抑えられ、褐変を遅らせることができるのです。
そして、食塩をひとつまみ(お湯の約1~2%)入れると、クロロフィルの分子の一部分が、食塩の成分であるナトリウムイオンと部分的に置き換えられて、安定したかたちになると同時に、酸化酵素の作用を多少おさえる効果が期待でき、色鮮やかに仕上がります。
またお湯の量も重要で、お湯の量が少ないと青野菜を入れた時に大幅に温度が下がってしまい、ふたたび沸騰するまでに時間がかかってしまうことで褐変し、組織が柔らかくなりすぎて食感が悪くなるので、青野菜の量の5倍以上のお湯を使用することをおすすめします。
きゅうりは板ずりと塩もみでおいしさを引き出す
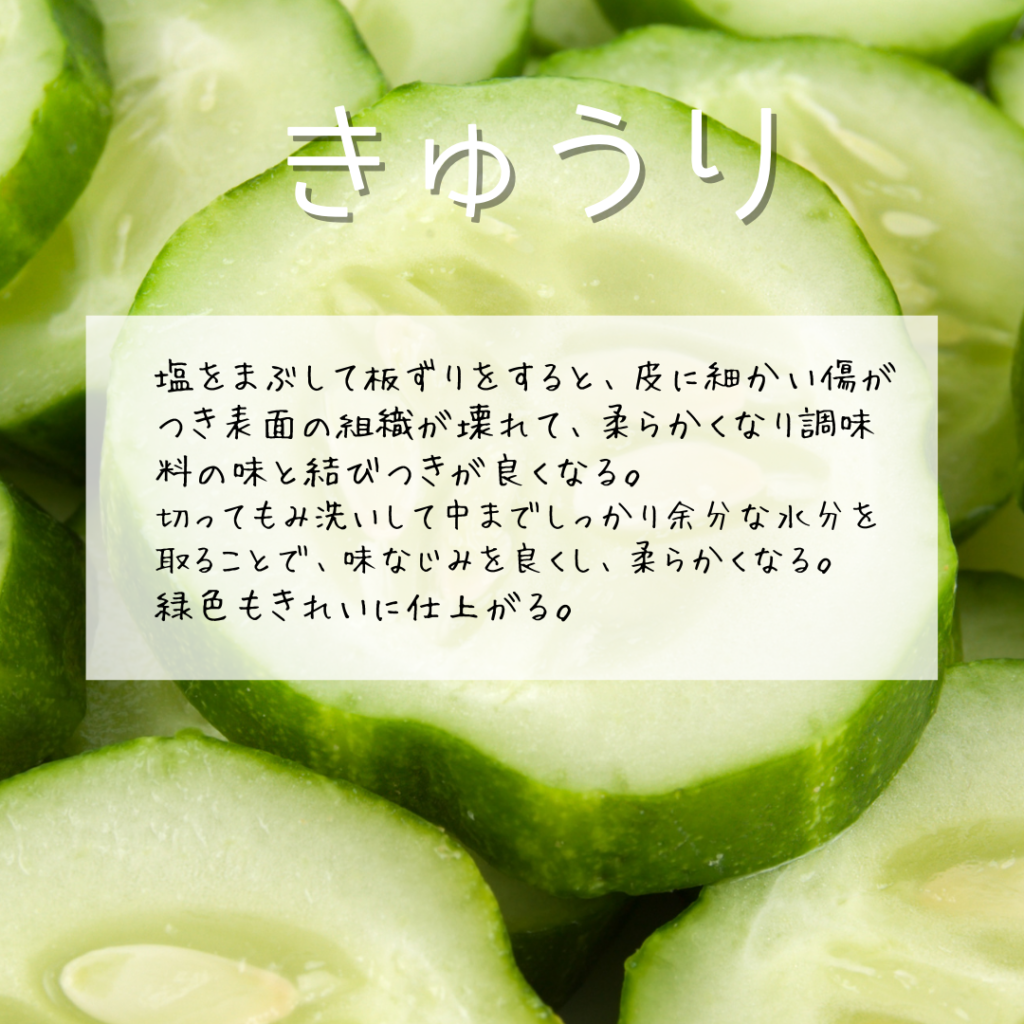
野菜に塩をもみこむことで、浸透圧により細胞の水分が引き出されます。水分を引き出すことで柔らかくなり、味がしみ込みやすくなるという良い効果が期待できるのです。
特にきゅうりは皮の部分の組織が固く丈夫なので、大きく切ってドレッシングをかけても、皮の部分は味がなじみにくくなっています。そこで、塩をふって板ずりすると、いぼが取れ、表面の組織が少し壊れて、調味料がなじみやすくなるのです。またクロロフィルとも相性が良いため色も鮮やかに仕上がります。
ポテトサラダなどで使用するときは、きゅうりを切ってからしんなりするまで塩もみして、水けを絞り出し、水洗いで塩気を抜いて使用しましょう。そうすることで、きゅうりの青臭さが抜け、味が馴染みやすくなり、良い引き立て役になります。
たまねぎは塩もみで辛みを抜く
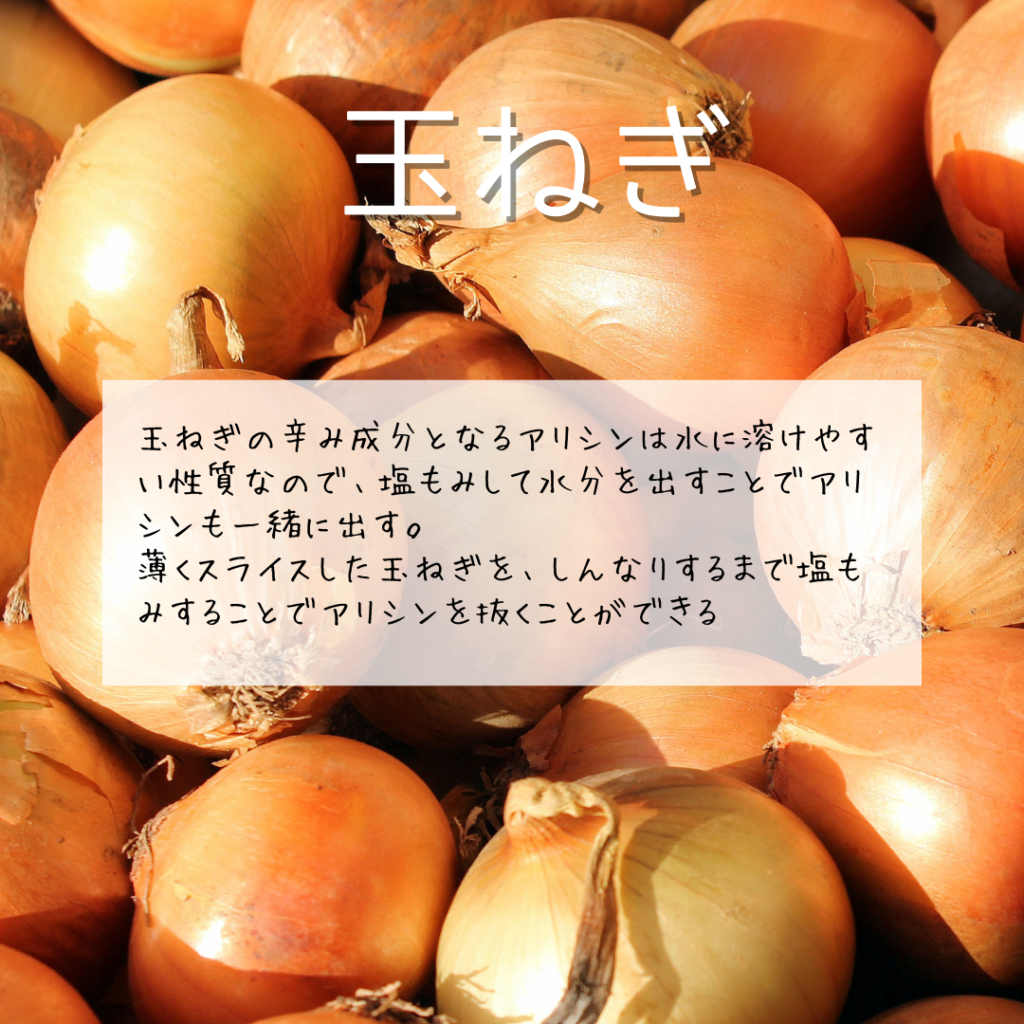
たまねぎには硫化アリルの一種”アリシン”という成分があり、その成分が辛みや催涙効果に関係しています。
アリシンは水に溶けやすい性質があるので、塩もみをして浸透圧により玉ねぎの水分を出すことでアリシンも出ていくのです。
きゅうりと同じでしんなりするのでポテトサラダなどに入れることで主張を押さえ良い引き立て役になってくれます。逆に、たまねぎのシャキシャキ感がほしいのであれば塩もみさず水にさらして辛みを抜きましょう。
しかし、アリシンは健康的に重要な成分で、血液をさらさらにしてくれたり、消化液の分泌を助ける作用があるので、あまり抜きすぎない方が良いことも覚えておいてください。
サンドイッチにはさむ野菜に塩ふり
サンドイッチにレタスなどの野菜をはさむと、野菜の水分が出てパンに吸収され水っぽくなってしまいます。
パンにバターをぬることである程度防げますが、野菜に塩を振って脱水することでさらに状態が良くなるのです。
野菜に2~3%程度の塩を振り、15~20分ほど置いておくと浸透圧の関係で強制的に水分を外へ引き出せます。あとは引き出した水分をキッチンペーパーでふき取れば水っぽくなることはないでしょう。お弁当などでサンドイッチを持っていくときはしっかり水抜きをしておくといいですね。
まとめ
塩と野菜の関係
- 茹でる時に塩を入れて色鮮やかにする
- 塩もみをして余分な水分を出す
塩は味付けだけではなく、上手に使うことで野菜の良さを引き出すことができるということが分かったと思います。
野菜のほかにも塩の活用法は多くなるので他の記事もチェックしてみてくださいね。


